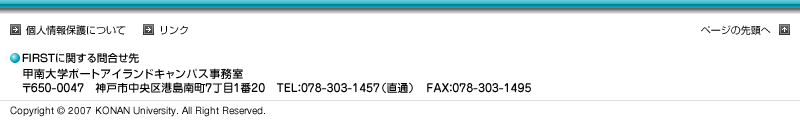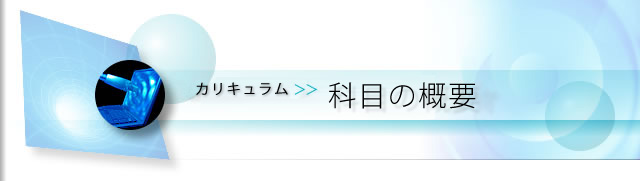| 科目名 | ナノバイオサイエンス序論 |
|---|---|
| 配当年次 | 1年次(前期) |
| 単位数・科目 | 2・必修 |
| 曜日・時限 | 水曜1限 |
| 担当教員 | 三好 大輔 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 生命は細胞の集合体であり、細胞は分子の集合体である。すなわち、生命体は、非常に精巧に形づくられた分子集合体である。このような非常に精巧な生命(バイオ)に学び、ナノスケールの新材料を開発することが、ナノバイオサイエンスにおける目標の一つにある。また、ナノテクノロジーを用いて、生命体の仕組みを理解したり、医療・健康・食品などに貢献することもナノバイオサイエンスに課された課題である。本講義では、ナノとバイオの基礎となる分子を学ぶことにより、バイオでナノに貢献する、ナノでバイオを解明する方法を学ぶ。ナノテクノロジーとバイオテクノロジーを融合させる必要性について理解する。さらに、ナノバイオテクノロジーの概要と要素技術について理解することを目標とする。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 化学や分子の視点からナノとバイオの共通点や相違点について理解する。ナノバイオパックを履修するために必要な基礎知識や考え方を習得する。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 出席、レポート、期末試験を総合して評価する。また、理解度を確認する小テストを行う場合がある。 |
| 講義構成 |
1.ナノバイオテクノロジーとナノバイオサイエンスとは 2.生命の機能を担う細胞と分子 3.細胞内小器官と細胞内分子環境 4.生命を構成する分子の構造:核酸 5.生命を構成する分子の構造:タンパク質 6.生命を構成する分子の構造:糖鎖、代謝産物、情報伝達物質など 7.セントラルドグマとヒトゲノム計画 8.物質の形と機能を決める相互作用 9.化学平衡の基礎 10.生体分子解析方法の基礎 11.生体分子の自己組織化とナノバイオサイエンス 12.まとめ |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | ナノテクのためのバイオ入門 荻野 俊郎、宇理須 恒雄、日本表面科学会 編集 共立出版 「医療ナノテクノロジー」片岡一則監修 杏林図書 「ナノバイオテクノロジー」丸山厚 監訳 NTS |
| 備考 | 講義内容は非常に広範にわたります。有用な材料や素子を開発することを目的とするナノサイエンスの立場から、生命やバイオの面白さと有用性を見直してみましょう。逆に、複雑な情報と機能を研究するバイオサイエンスの立場から、新しいナノ材料やナノ素子を考えてみましょう。 |
|