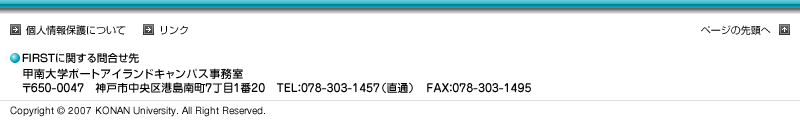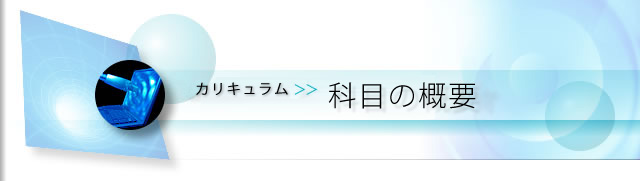| 科目名 | アドバンストマテリアル |
|---|---|
| 配当年次 | 2年次(D期) |
| 単位数・科目 | 2・選択 |
| 曜日・時限 | 水曜1限、金曜2限 |
| 担当教員 | 赤松 謙祐、林 高史 |
| 講義方法 | 講義 |
| 概要 | 本講義では、将来実用化が期待される機能材料の合成法、構造および機能について述べ、特に最先端のナノ構造材料に関する応用例について、無機および有機材料に分けて講述する。 (赤松) 有用な機能を有する人工材料は単体でその機能を十分に発揮するものは比較的少なく、通常いくつかの材料を組み合わせた複合材料として用いられる場合が多い。これら材料の機械的、熱的、化学的、光学的および電気的性質を利用して高度な機能を発現する機能性材料の合成法、機能発現のメカニズムおよびその応用について解説する。特にセラミックス、ナノ粒子などの機能性材料を例に口述する。 (林) 色素は、我々日常の生活に欠かせない素材である。一方、自然界を眺めても様々な色素が存在する。たとえば、植物の葉の緑色や我々の血液の赤色はクロロフィルやポルフィリンと呼ばれる大環状芳香族化合物に由来する。さらにこれらの色素は金属イオンに対する配位能を有し、単に色を呈するだけでなく、様々な機能を発現している。本講義では、生体内に多く存在する色素の基本構造であるポルフィリンの有機化学・錯体化学的な解説とともに、ポルフィリン骨格を含む天然の色素の機能と構造を分子レベルで説明した上で、生体機能材料への応用について紹介する。 |
| 講義の目的と学生の理解・達成目標 | 様々な機能を有する無機材料、有機材料のナノ構造と機能の相関について原子・分子レベルで理解するとともに、将来的に実用化が望まれる材料の機能、模索されている合成手法等に関する知識を習得する。 |
| 関連学問 |
生物 化学 物理 |
| 関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
| 成績評価 | 出席、レポート提出および期末試験により総合的に評価する。 |
| 講義構成 |
(赤松) 1.序論「無機機能性材料」 2.材料合成手法 3.複合化による機能発現 4.無機ナノ粒子:合成と機能 5.機能材料1:無機半導体と発光材料 6.機能材料2:記憶材料、センサー、電池 7.機能材料3:有機・無機ハイブリッド 8.次世代機能性材料の動向と展望 (林) 1.序論「生体機能性材料」 2.生体内色素の紹介:ヘム、クロロフィル、ビタミンB12 3.酵素保持タンパク質ミオグロビン・ヘモグロビンと人工血液の将来性 4.光合成のしくみ 5.人工光合成系構築への挑戦 6.天然色素を有する酵素の紹介 7.次世代生体機能性材料の動向と展望 |
| 教科書 | なし |
| 参考書・資料 | 必要に応じて適宜配布する |
| 備考 |
|